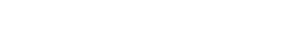演劇と会話教育
*法政英語英米文学研究会紀要PHOEBUSに掲載された、演劇を念頭に置いた会話教育案の概説です。
1)運用面の課題
1−1 講義型授業の実状
英語文法の権威的文献の一つにさえ、言語を学習する者に共通する悩みが記されている。
Usually, he already has grounding in the grammar of the language after several years of school English. Yet his proficiency in actually using the language may be disappointing. This, we believe, may be partly attributed to ‘grammar fatigue.’ 1
外国語の学習は、文法の理解と切り離しては考えられない。ただ、文法が理解できていても実際の運用能力、つまり actually using the language における能力を身につけている学生が少ないのも事実である。本稿ではその原因と打開案を探り、教員としてどのようなポイントに留意すれば「文法の理解だけで疲弊」させてしまうような授業ではなく、運用面でも成果が現れるような指導ができるかを考えていきたい。
本来、文法事項などの理解と実際の運用とは別の能力であり、調整を施さないかぎり、両者を相互的に発展させることは難しいのではないだろうか。
こういった印象を強めたのは、私が担当している大学生の英語(主に一年生の表現系の英語)の授業の一つの課題として、学生たちに教科書に掲載されている英会話をベースに「続きの会話」を自由に作らせたときの様子を目にして以降である。学習内容の復習も兼ねて、授業の終わりにグループに分けて書かせたのだが、授業で得た文法事項を使うことを意識し過ぎるあまり、内容を「書くことのできる(自分が知っている)英語表現」に合わせるかのように制限を掛けて作文をしている学生が目についた。自由度の高いタスクを課したはずが、逆に非常に窮屈な作業になっているようだ。英語表現に興味のある学生ですらこの調子で、まして英語自体が不得意な学生については、まるで最初から作業自体の方向が見出せないまま動きが止まってしまうことが多かった。語彙や文法の知識が豊富で正確だとしても、考える力が備わっていなければ「表現する」という行為は結びつきにくい(松本)という指摘通り、自ら考え構成する力は語学を学習する場でも求められるだろう。ここでは第二言語を習得する過程で学習者に「考えさせる」ことを第一の目的に、演劇的手法も参照しながら、有効な手立てを整理してみようと思う。
1−2 理解と運用の違い
講義形式の授業では一般的に「教員の説明を受け止め咀嚼する」受動的な姿勢がその基本となる。対して「自ら作業をしながら」行なう運用の練習には能動的な姿勢が求められる。理論がわかっていても実際に使いこなすことができない。これは道具の使用やスポーツなど、学習行為の多くに共通して見られる状況であり、会得した理論に即し、イメージ通りに身体を動かせないのは、習得の段階にある人とっては当然かもしれない。
表現系の教科書の単元は一般的に「語彙」「会話のリスニング」「文法の解説」「部分補充の英作文」の4つの項目で構成されていることが多い。応用としてやや難易度の高いリスニング問題が加えられている場合もあるし、音読を念頭に置いた発音に関する説明が記されているものも見られる。学生は用例を通して知識をインプットし、問題に解答することで定着を図るというのがほとんどの教科書の編集意図だろう。これらの手順に則って学習することで学力は身につくはずだが、ここではあえて、これらの諸課題に対応するだけでは十分に体得できないものを想定することで論点を明確にしたい。
教科書に沿って練習を重ねるだけで得ることの難しいものの一つが能動性の高い学習経験であり、教師が授業の中で新たに指導を追加することによってその実現が期待される項目である。そしてこの能動的な取り組みこそ、語学の運用力を高めるために不可欠な要素だろう。
実際の会話は当然ながら、教科書に記載されている雛形の通りには進行しない。教科書における会話を利用して空所を補ったり、部分的に変更するような作業をこなすだけでは、知識はインプットされるが、運用力が身に付かない学生もいるのではないだろうか。また語彙や法則を把握することで得た能力は、あくまで教科書の構成や単元といった条件のもとでの行使に留まる可能性もあり、学習範囲については広げていくべき余地がありそうに思われる。
上に述べたような学習の作業理念は「反復」である。正解を再現することを第一目的とし、「反応」つまり解答過程における独自の思考や解答以降の発展は、授業を任された教員が付け加える指示、そして学習者の主体性に託される。ただ、このような指導法が採択されるのも仕方ない状況もあるだろう。大人数のクラスで行なわれる一斉授業がそれである。
1−3 クラスサイズの問題
学生数が多いと一斉授業の方式に頼らざるをえないのは言うまでもないことである。クラスサイズについての指摘は、大学英語教育学会から成る「実態調査委員会2003」の報告にも含まれており、そこでは大学の英語教師の42%以上が「クラスサイズが大きすぎる」ことを改善すべき課題として挙げている(ちなみに調査対象の教員のクラス人数は21−30人が25.2%、31−40人が26.3%、41−50人が21.6%)。
学生数が多すぎると、具体的には「学生たちの制御や個別対応が難しく、学生同士の活動に支障がある」(Hayes)また「Speaking、Reading、Writingなどのタスクが滞り、名前や行動が把握できず、添削がままならない」(Locastro)といった問題が発生し、会話演習についても困難を極め、全員が正しく音読できているかすら確かに判別できないという状況が考えられる。
1−4 個人的側面の見直し
さらに加えるなら、言語活動は非常に個人的な側面を持っているはずであり、その意味でも一斉授業から得られる成果には限界があるように思われる。言語自体は社会に根ざした普遍的なコミュニケーション手段であるが、それを使用するのは個人であって、それぞれの環境や経緯がそこに反映し、複数の人が交わす「会話」についてもそれぞれに固有の人間が関わる。会話の動機についても公的な背景と無関係ではないが、私的な事情に端を発するほうが日常的だと思われる。
一斉授業で取り上げられる対話には、個別の「必然性」が入り込む余地がどうしても少なくなる。この必然の弱さが、学生たちにとって会話の習得が促進されない理由の一つになっていないだろうか。私たちがなぜ母国語を理解し、使いこなせるようになったのかを考えてみるといい。母国語を習得するプロセスと第二言語を学ぶプロセスとの違いに注目した場合まず気づくのは、反復の量であり質だろう。親子や家族という同じ関係性、時々刻々少しずつ異なる設定において、量的に幾度も繰り返され固有のシステムができていく。一方、質的な特徴としては、必然性の強さが挙げられるだろう。言語を習得しつつある子供にとって「苦痛」や「空腹」あるいは「眠気」のような欲求は、どうしても相手に伝え、理解され解決されないといけないという切迫した必然が備わっているからだ。これらの固有性は反復を単なる機械的な動作に納めずに、主体的な広がりを含む反応の域に押し上げてくれる。
また表情や仕草などの非言語的な信号の授受も、コミュニケーションにおいては欠かせない要因である。言語の習得には、こういった幾つものアプローチの相互的な機能が求められるだろう。ただこのような状況や関係を、実際に授業内で作ることはやはり難しい。
また、必然性の弱い状況下で言語を一定時間に渡って耳にしたとしても、当人の言語システムが動かされないかぎり、十分な習得には至らないということも言える。必然性が弱ければ量的反復すらなかなか実現できないかもしれない。また若年層においては、母国語における言語システムすら未だ確立されているかどうか疑わしい場合もあるだろう。英語のみによって進行される授業が導入されても、まず母国語での言語システムが形成されていないと、システム間の混乱が生じる危険性もある。
さらに運用力を手に入れたところで、学校や会社における日常生活において、自らの言語システムを適用し変換せざるをない機会がどの程度あるのかも気になるところであり、こういった「発揮の必然」についても個人の事情が関わってきそうだ。日本で暮らす人にとって、日常的に英語を「使わざるを得ない」場面がどれほどあるのか。環境においても運用力が保持しづらいと言えるかもしれない。
諸々の課題を克服するには、改めてまず個人の内側に目を向け「第二言語の習得が是が非でも必要だ」という精神状態を創出するしかないだろう。そのためには想像力、換言すれば演技のようなものが必要になってくる。「人間は一人一人異なった自己概念と現状認識を内に持ち、それに基づいて行動する」という人間学的心理学の見地からの指摘(Rogers)に立ち返り、個人として強く必然を意識できる会話学習を実現するため、ドラマの効用を見直していきたい。
2)演劇的要素の導入
2−1 「役」と個人
英会話のみならず語学は、意志の伝達や自己表現に関わる言語を扱う学問である。運用も視野に入れて考えた場合は発信だけでなく相手の情報を汲み取り、周囲の状況やこの瞬間に至る経緯などについてもある程度は頭に入れないといけないだろう。元来こういった流れや呼吸のようなものは、特に会話学習の実際性を問題にするまでもなく、言語の本質として認識されるべきであり、指導や作業に際して常に優先されるべき項目である。
他者と自己との関わりを目的の一つに掲げるとき、演劇的な視点と方法論に可能性を求めるのは妥当なことのように思われる。
演劇と語学学習との共通点としては、まず「役」つまり「個人」の確立が挙げられる。現実の会話において人は、匿名的な一学生ではなく個人として関係を図るからだ。また時間的・空間的な情報に誘導されながら言動を展開させていく点でも、演劇行動との類似が見受けられる。
Acculturated individuals come to expect particular, relatively standard participation frameworks in given settings. Participants’ footing can often be predicted, once one knows their roles and the type of event going on. 2
引用中にある footing という語は、人同士の社会的相互作用を演劇的視点から説明する際にGoffmanが用いたもので、日常の様々な場面で人が、他者に対し(意識的であろうと無意識であろうと)取ることになる位置を意味している。これは「演技」という概念が、自分と掛け離れたものを演じる行為だけでなく、相手や場との関係を読み取ることによって自らの立場や肩書きを認識し、再定義しながら行動するという「ごく日常的な行為」にまで拡大できることを示している。関係性を重視することによってそれぞれの振る舞い方が意識され、ほとんど全ての身近な行為に演技的要素が入ってくるという考え方だ。
語学学習の場であっても、他者との関係や設定が漠然としたままでは、課題としてのコミュニケーションの遂行にも不具合が生まれるだろうし、また取り組みを推進する動機や興味もそれほどは育まれないだろう。言語が外界との疎通の手段であるかぎり、その使用に先立って他者との関係=自分の位置を確認することは前提とも言え、それは演劇における「配役」とも無関係では無い。「社会性・共同性の学習」といった演劇教育の理念(富田)が加わって初めて、個別の必然を備える会話が実現に近づくのではないだろうか。
ここで自己規定について確認しておくほうがいいだろう。他者との関係の一端は自分であり、繋がりの中でどんな役を担えばやりとりがスムーズに持続するのか、自覚的になってみるのである。そうすれば、その「役」にとって必要な言葉が自ずと生み出され、他者についても活かされた自然なコミュニケーションが成立し、運用面でも効果を約束してくれる自己という「役」が確定するはずである。加えて、話し相手に興味を持ってもらえるような話題を提供できるように日常を少し見直してみることこそ、自己を再規定することになる。
2−2 日常の捉え直し
私が脚本家として所属している日本劇作家協会の脚本講座「戯曲セミナー」での指導経験から、自己規定の方法の一つを取り上げてみよう。戯曲セミナーの開講当初は、井上ひさし・別役実・いとうせいこう・ケラリーノサンドロヴィッチ各氏と共に、いわゆるコントに限った指導をさせてもらっていたが、現在では年に1〜2回の長めの劇作品/ストレートプレイを含めた講義と簡単な演習、受講生の提出作品の添削、そして俳優・芸人の方々を読み手に迎えてのリーディング公演の司会運営が主な職務となっている。セミナーの受講者は一般の会社員や公務員、主婦、学生から若手作家、俳優の方まで様々だが、おしなべて「作品を書きたい」という動機は持っている。ただ大半の人が「どう書き出せばいいのか」きっかけを掴めないでいることも否めず、指導のポイントも最初の一歩をどう踏み出させるかが重要になってくる。
そこで受講生には近年「劇作とは日常の捉え直しである」という切り口を講義の初めに呈示し、できるだけ気負わずに取り組んでもらえるよう考慮している。ブログなどの手軽さを例に引用し、最初から奇を衒ったようなものを書こうとせず、まずは「自分と自分の境遇をプレゼンテーションする」だけで十分に自己表現に値するし、そこに少しばかりの構成・演出を施せば他者の鑑賞に堪えうる「演劇的なスタンス」が得られるといった着想である。
重要なのは、身近な現実を見渡し、書きたいことに自然に「気づく」ことで、気づいた素材には表現に足りる必然が確かに備わっており、伝達の方向を揺るがさずに維持できるはずだ。伝えたいことさえ確かに存在していれば、手段の違いはさほど重要ではない。逆に伝えたいことが曖昧なままで表現の手段を決めることは難しい。母国語で表現するのか、第二言語で表現するのか、伝え方の決定は然るべき段階まで保留にしておけばいい。素材が身近だと、学習者にとってのリアリティや必然が実感しやすく、自ら考えることも促され、内容が伝わるかどうかが最大の関心事になってくれる。このプロセスが、戯曲作りや会話作りに必要な自己を再発見させてくれるに違いない。
2−3 自己規定と演技
また演技のワークショップについても、演劇ぶっく社主催の「エンブゼミナール」やサンミュージック・プロダクションでの指導をはじめ20年来、様々な機会を与えられているが、そこでも数人のグループによる自己規定をゴールに据えたオリジナルのワークを随時行なっている。
これらもそのまま語学の授業で行なう会話作りに適用できるのだが、自分というキャラクターをその場にリアルに存在させるための演技レッスンの一つで、「忘れられてしまった自分を思い出してもらうため、できるだけ多くの特徴を他者にアピールする」というオリジナルのエチュード(即興練習)がある。用意される設定としては、全員が本人のまま(別の人物を演じることはせず)「お互い半年ぶりに出会った」というもので、彼らのうち一人だけが名前もキャラクターも忘れられており、他の全員に「自分がどんな人間なのか」名前や出自、覚えてもらっているはずの外見や内面の特徴、また自分らしいエピソードやプロフィールを主張していく。それに対し他者は一人ずつそれぞれの特徴をきっかけに当人を思い出していくという流れなのだが、「思い出してもらう」という必然、「実際の自分の特徴である」というリアリティに加え、「自分がどう見られているのか」という客観的視点が当人に感得されていくので、会話は交わされつつ安定感を増していく。また「呈示していく特徴の順番はどうするのか」という構成力も身に付いていくだろう。そして忘れている演技と思い出させる演技が互いに繋がり、「演者間の呼吸」にも触れることができる。演技のエクササイズではあるものの、必然や客観性、そして構成力によって支えられた会話が求める言語は、会話作り全般に役立つ普遍性を持っている。
2−4 予想と音声
外国語が聴き取れないとき、我々は単に語句が聴き取れないのではなく、思考が会話の進行(速さ)に就いていかず、受信/発信の別無く「言語の組み立てが間に合わない」のではないだろうか。これは相手がどんな語句を口にする可能性があるのか、どんな会話がこの場に起こりうるのか、そういった想像がタイムリーになされていない点に理由がある。「状況が言わせそうなこと」がわかっていれば次にどんなことを言われ、それに対して自分はどう返せばいいのか、短い時間であっても予想がなされ、やりとりの準備ができるはずである。このような予想機能こそ、客観的に自分たちの会話を見渡し構成を行ない、相手との関係や呼吸から逆算的に必要とされる言語を採用していく「会話活動」の賜物である。そしてこういった機能は、母国語での日常会話、日ごろ使っている言語システムには習慣的に備わっているもので、誰しもごく自然に予想や反応を重ねながら発展させてきたにちがいない。
また言語を読んで理解する場合、我々はそれぞれの言葉について自分の頭の中にある抽象的な音をイメージしている。これは実際に他者が発する言葉の音とは異なるはずである(日本演劇教育連盟)。会話の過程で、他者から発せられた言語を瞬時に分析し、自分の言語イメージと符合させることで初めてその意味が理解できるわけで、抽象的なイメージなら日ごろから理解していても、他者の肉声の場合は聞いてわかるまでにタイムラグが生じるかもしれないのだ。
演劇的アプローチの中で、言語に音(声)が重ねられ、また仕草や表情などの非言語的要素が加えられることで、ようやくコミュニケーションの構造が完成する。それは手間のかかる総合化だろうが、一方で確かなイメージを交わすためにマスターするべきものである。
2−5 協同学習
演劇的な作業は、協同学習の主体的進行も手伝ってくれるだろう。学生が「お客」の側も「演者」の側も超えて「作り手」の側に立つ機会(亘野)を設けてくれるからである。これは講義型授業の「受動的理解」と「再現」に相当する部分が融合して「作り手」のレベルに移ることに相当する。
またグループワークが軌道に乗れば、大人数のクラスでも班ごとに自律しながら演習に取り組めるので、教員はファシリテーターとしてヒントやアドバイスを与える形で流れを作ることに専念でき、一斉授業のように全学生に一律の行動を取らせる必要は少なくなる。学生本人が運営者としての責任を感じるようになり、発信を見据えた知識の整理や必然性を備えた学習が本人たちの意志に促され、クラスサイズが大きすぎることから生じる問題も解消されるにちがいない。
3)授業例
今までの考察を元に、実際に大学で行なった授業の一つが、以下のような会話文の部分的英訳である。
3−1 自己規定
まず個々の学生に、動機や書きやすさを優先させ、自分の日常を隣席の学生に伝えることを目標に据え、自己を規定させる。用紙を配り、自己紹介に始まり興味のあるもの、英語の授業に対する思いなど「伝える必然」の強いものを日本語で書いてもらう。実際の境遇を写し取ればいいだけだが、まとまった文章自体を書くことに慣れていない学生も目につく。そういう場合は無理せず短い文章で箇条書きにさせる。それらの短文は英訳しても当然平易な文章になるわけで、結果的に「英語に直しやすい」文言が多くの割合を占めることになる。作文が苦手なほど英訳作業が簡単になるという現象がそこでは見られる。
3−2 他者を意識
二人一組になり、それぞれが書いた自己紹介文を見せ合い、感想を交わしながら組内でそれぞれの修正を行なう。この共同作業で重要なのは、自分の作成した文章が相手から見てどうなのか、冗長なのか逆に説明不足なのか、他者に対しどのくらい興味を引く内容なのか、客観性を意識しながら書き足したり削ぎ落したりする作業が行なわれることである。同時に他人に見せることで、あまりに粗末な内容は書きたくないという、最低基準のようなものが本人の気持ちの中に設定されていくのが興味深い。
修正が済めば、教員は一度用紙を回収して内容に目を通し「組ごとに作る会話のテーマ」「時間的、空間的設定の案」を組ごとに記した上で返却する。この段階で初めて手本となる会話(全学生共通)を告示する。会話を完成させたいというニーズが高まっているので、聴いている学生たちの真剣度が違う。そのあと学生は組ごとに用紙を持ち帰り(組んだ相手の用紙もコピーし、自分のものと計2枚の用紙を持ち帰る)次週の授業までに二人で連絡を取りながら、日本語の会話をある程度作ってくる。
組ごとによる作成を通し、客観性と共に責任感はもちろん、自分たちについての会話を作るということから、一斉授業では困難だった能動性の発動が期待できる指導法である。
3−3 会話の完成
二回目の授業では二人一組のグループ同士でさらに組んで四人一組となり、互いに自分たちが作って来た会話の日本文のうち英語に換えられそうな部分/語句に限って、英語に直させる。とりあえず品詞や細かい使い方は間違ってもいいので、辞書を用いたり四人で意見を出し合うことで、客観的な視点から実状に即した二つの会話ができあがるはずである。そこに使われているフレーズは、作成者である学生本人にとって事実であり、自分をわかってもらうために伝えなくてはならない情報であり、互いの関係(役)を意識しながら組み立てられた「活きた台詞群」である。
3−4 発表
完成した英語台本を声に出して読ませてみる。発表の順番も決め、教室の緊張感を高める。発表準備の際にトライさせたいのは(教員の特性にもよるので演劇的レベルは度外視していいが)感情表現である。現実の会話同様、表情や仕草、つまり非言語的な手段によってニュアンスを加え、内容がより明確に伝わり、会話がより魅力的に展開する様子を実感してほしい。それがコミュニケーションの第一歩であり、かつ最終目標でもあるからだ。最初に、表現が特に上手な学生の組にプレゼンさせると盛り上がるだろう。仕上げの段階で一気に読み方(発音、強弱、切り方)を指示しなければならないが、この時点でも「伝えたい」という必然が強まっているので素直で熱心な学習が期待できる。
3−5 演出的経験
四人一組にした意図は、発表の前後(一回目の発表のあと修正を加え二回目の発表を行なう)に一組の会話に対し、もう一組が感想を言ったりアドバイスを行なう(演出する)ことで、互いに会話作りのポイントやコツを客観的に理解しやすいことにある。
実際に動き、言葉を発することで、会話がうまく機能しているか否かは全員にとって瞭然であり、改善がなされたらそのぶん目に見えてわかるのでやり甲斐も感じられるだろう。
4)まとめ
能動性と現実性、共同作業のそれぞれに「必然性」が裏付けされているのがこの手法の特徴だろう。「適切に伝えるとは、場面や状況、相手の反応などを踏まえながら、自分が伝えたいと思うことを、相手に伝わるようにすることを意味する」(向後)という分析通り、英語をより効果的に学習するために重要なのは、伝達や表現を練習することによって自己の再規定や言語システムの安定を確実なものにすることだと思われる。
今後も導入部の動機付けや、途中段階のアドバイスの方法などを精査、改善し、データの収集も念頭に置きながら、演劇的要素を盛り込んだ言語習得法を試行し提案していきたい。
引用文献
Leech, G. and Svartvik, J., Communicative Grammar of English, London: Longman, 1975.
Wortham, Stanton E.F. Acting Out Participant Examples in the Classroom, Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 1994.
大学英語教育学会実態調査委員会『わが国の外国語・英語教育に関する実体の総合的研究―大学の外国語・英語教員個人篇』丹精社、2003年。
参考文献
Bryam, Michael and Fleming, Michael ed. Language Learning in Intercultural Perspective, UK: Cambridge UP, 1998.
Hayes, David “Helping Teachers to Cope with Large Classes,” ELTJournal 51(2), pp.77-84. 1997.
Locastro, Virginia “Large Classes and Student Learning,” TESOL Quarterly 35(3), pp.493-496. 2001.
Krashen, D. Stephen Explorations in Language Acquisition, NH: Heinemann, 2003.
Rogers, Carl. R. Client Centered Therapy. Boston: Houghton Mifflin Company, 1951.
Tarone, Elaine E., Gass, Susan M. and Cohen, Andrew D. ed. Research Methodology in Second-Language Acquisition, NJ: Lawrence Erlbaum associates, Pub., 1994.
E, Goffman, 石黒毅訳『行為と演技』誠信書房、1974年。
JACETバイリンガリズム研究会編『日本のバイリンガル教育』三修社、2003年。
黒川泰男『英文法再発見』下巻 三友社出版、1987年。
向後秀明(2011)『英語教育』2011年7月号, p.12。
佐野正之『アクション・リサーチのすすめ』大修館書店、2000年。
鈴木佑治、吉田研作、霜崎實、田中茂範『コミュニケーションとしての英語教育論』アルク、1997年。
竹蓋幸生、水光雅則『これからの大学英語教育』岩波書店、2005年。
富田博之『演劇教育』国土社、1990年。
日本演劇教育連盟編『新演劇入門』晩成書房、1990年。
晩成書房『演劇と教育』1986年8月臨時増刊号。
松本茂(2009)『英語教育』2009年7月号, p.11。
亘野陽一(2010)『英語教育』2010年7月号, p.31。
米山朝二、佐野正之『新しい英語科教育法』大修館書店、1983年。