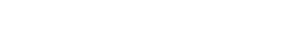『放送文化』(NHK出版)連載の書評的コラム
「Culture Box」
書きたいことが一杯で、その本と同じぐらいのページ数になってしまうことも多々あったね!それゆえ視点を絞ってお送りするホンネタ集。
2002年10月号掲載『耳のこり』(ナンシー関著 朝日新聞社)
評して参りました。書評ってことで。今回この「評する」ことを少し考えてみたい。そうさせたのはナンシー関。作品や現象を説明したり伝えたりってだけじゃなく、その本質をすくい取る。そのすくい取り方に評者の個性が見方が出る。ナンシー関の、端的に本質を言い当てる言葉の選び方はやっぱり見事だと思う。本質とは隠されていなければならない。掘り起こされるべきものだから。ハゲにハゲと言っても本質を掘り起こしちゃいない。少しハゲかけてる人をハゲと言って初めて本質ウオッチャーとなる。いかがわしい、胡散臭い、虚飾・・TV自体が、そういった隠された人間性を明からさまにすることを目指し、発展してきたメディア。そう、TVはナンシーで完成されつつあったのかもしれない。なんて気がする。彼女の消しゴム版画は濃縮された人間TVのワンカット。刃が向けられるのは自信満々な発言。深田恭子の「前々世はマリー・アントワネット、前世はイルカ」という発言に「悪女と深田の間に、人間に奉仕する(ってことらしい)イルカをはさんでリセットしてる」ことに「チェック欲をかきたれられる」とある。でもかきたててるのはTVでありタレントの方で、実は視聴者のチェックを待ち受けている。完成されるために。これからTVにまたぼんやりベールが掛かってしまうのか。娯楽の本質が隠されたままになってしまうのか。評し続けてほしかったものです。
2002年9月号掲載『日本言論世界激動編』(爆笑問題著 幻冬舎)
立場か変わると笑えることがある。医者が患者に治される。「どうしました?」「どうも最近人を診療してしまうんです」ここでコントを書くスペースは無いが、言いたいのは立場変換の面白さ。警官が泥棒に捕まえられる、教師が生徒に教えられる・・
『日本言論』。読んでくうちに気づいたのは、漫才では突っ込みとして聞くパート、つまり田中さんの言葉が、事件の凝縮された紹介/説明として、より大切になってきてること。「フリ」である田中さんの事件レポートを、太田さんと読者(客)が聞くことから爆笑問題の世界は始まるって感覚。そういえば太田さんのギャグって、客席からの無責任で無邪気なヤジって気がする。「衝突したアメリカの原子力潜水艦、ソナー要員に訓練生が入っててモニターも故障してた」「今ならアメリカに戦争で勝てる」なんてヤリトリなんてまさにそう。変に前向きなズレ、「わかってない」人が演じられて漫才形式が続く。簡単に見えてとても技術の要る作り、そして社会事件をネタにするときこれ以上無いアプローチだと思う。「爆弾作った少年が危険物取り扱いの免許を持ってた」「お前が危険なんだ。取り扱ってる場合じゃない、取り扱われろ」・・立場が変わる。視点が変わる。生き生きとしたヤジの形を借りて、物の見方を自由に変えていく。柔らかな情報対応。私たちのお手本になる一冊かもしれない。
2002年8月号掲載『毎日一人は面白い・・』(中野翠著 講談社)
雑貨店に入ると、周りをぐるりと取り囲んでいる陶器やらアクセサリーやらロウソクやらを見回して嬉しそうに輝く。・・そんな友人がいる。私はどちらかと言うと、並べてあるセットのミニ人形を一人背中向けにしたり、ポケットに入っていた輪ゴムを意味無く棚に置いてみるなどして、雑貨以外の所で楽しみを見つけるタイプだろうが、そしてそんな「タイプ」なんて無いが、雑多な物が同列にずらーっと並んでいるあの陳列棚になんとも愛情を感じてしまう気持ちはわからないでもない。映画俳優、落語家、ワイドショー出演者から一円玉強盗や年賀状泥棒などのおかしな犯罪者、そして町を歩いてて見かけた気になる人・・32才の顔に17才の格好の女の子、ジジマゴカップル、浮世離れした古本屋トリオたち。そんな雑多な人間たちが、おんなじ目線で描かれていくんだけど、何よりそこには好奇心のフットワークが躍動、決して飽きない陳列雑貨。世界は賑やかでないと。日記風に一日ごとに書き足されていくので、日々の時間の流れが伝わってきて、例えば志ん朝さんが亡くなったショックは次の日も次の日もって続いていくし、こういう進み具合ってとても個人的でリアル、面白い。「三匹の犬を自転車に乗せて走っていくおじさん」の話を人から聞いたときの著者の一言が、読むうちに読者の気持ちの代弁になってくる・・「私も見たかった!」
2002年7月号掲載『ことばを磨く18の対話』(加賀美幸子編 NHK出版)
今回の書評だけは文章では伝えたくなかったわけです。文字の限界そして「声の可能性」。タイトルとなっている「ことば」、これは声として発せられる話し言葉のこと。アナウンサーである編者が、様々なジャンルの声のプロとの対談を通し、話し言葉の本質を彫り当てていく。その中で何人かの人が繰り返す「自然に」というスタイル。声なんて作ろうとしても不自然になるだけ、結局は内面の問題、「ゾウのことばを朗読するときはゾウの細胞になって」と話す岸田今日子さんを始め、共通するのが「演じない」という感覚。その方が「人」が立ってくる。存在そのものが伝わればいい。そして「自然」でいるためにどうしいたらいいのか。「稽古を重ねて自由になる」と言う市原悦子さん、「流れをつかんでそれに乗るだけ」と言うタモリさん。久米明さんは「一度リハーサルで涙を流しておけば、心にずっと湛えたものが、本番の語りの声の音色に出ます」・・・「自然」でいられるためには、経験から得られる極意が必要なんだ。声は人間を伝えてくれるんだけど、文字だとそのへんが・・この文を書いてる私が、満員電車でお年寄りに席を譲りまくる心優しい人物なのか、はたまた満員電車で携帯電話を掛けるマナー知らずなのか、読者は汲み取れない。文字の歯がゆさ。せめてもの思い、今声に出しながらこの書評を書いてます。
2002年6月号掲載『新しい単位』(世界単位認定協会編 扶桑社)
それにしてもシンプルなタイトル。内容も期待に違わずシンプル。一つの「新しい単位」につき、認定の経緯とその具体例が8つ。しかしそこに込められた遊びと本質。いや、やっぱり遊びだけか。そしてシンプルな構図の中にすくい取られた、細かい見どころ。実はなかなか入り組んだ面白さ。例えばこうだ。「器用さ」を表す単位として認定されたのは「シンニョー」。これは「漢字のしんにょうを綺麗に書きこなす器用さ」を1シンニョーとして基準化、使い方として「コンビニおにぎりを海苔を破かずに取り出す器用さ」を13シンニョー、「片足を上げたまま寝るフラミンゴの器用さ」を205シンニョー、そして多くの重病患者を治してしまうブラックジャックの器用さを4万1500シンニョー。こんな調子で、カクテルにパイナップルが乗っているのを「1パイナポウ」として測る「ゴージャスさ」、納豆に入っているカラシを捨てずに保管するせこさを「1カラシ」として測る「せこさ」などなど日常をピン留めするかのように繰り出される31の新しい単位。世の中を単純化、相対化していけばなんだかわかったような気になる。あの単位ってものの威力を実感せずにはいられない、そしてその実感もすぐに骨抜きになっていく、ぐにゃぐにゃなエンターテインメントが、かしこまった装丁に詰まってます。イラストも気合い入ってます。陰影がついてます。
2002年5月号掲載『なつかしのTV青春アルバム!』(文藝春秋)
著者が振り返る番組そしてヒーローたち。仮面ライダー、ライオン丸、必殺仕事人、松田優作・・・なんとなく4つ挙げてみただけで十分濃厚だ。肉、肉、魚、肉・・・といった感じですっかり野菜不足だ。この濃厚な存在感のわけは人間のアンバランス。今なら視聴者の好みなんかをリサーチしたり、前に当たったパターンをコピーしてみたり、っていう最大公約数的な作り方もあるみたいだけど、当時は作り手の思いが熱く噴き出す余り「とらわれない」ヒーロー像が出来上がってしまう。悪に作られたヒーロー、思い悩む悪人、そして最終回はヒーローが死んでしまうし。それも「自己犠牲」みたいなものばかりじゃなく、「傷だらけの天使」みたいなかっこ悪い死に方も描かれる。やり切れない。でもだからこそ、見てる人が本気で共感できた。BGVのように見流せる共感ではなく、ほんと汗と涙、体力を使う共感。あの頃は「時代は変わる」という信念が崩れ去って、やり切れなさが渦巻き、でも何かを託せる新しい存在を模索する時代だった、と人は言う。そういえば私も当時、幼稚園で「仮面ライダーごっこ」を繰り返しながら新しい価値観やらアイデンティティやらを模索しておりました。哀しいかな今も模索しております。そして今も野菜不足。
時代の思いが人間やロボットの形になっていた頃のアンソロジー。
2002年4月号掲載『されどテレビ半世紀』(ばばこういち著 リベルタ出版)
力強く答える人、と言えば今の首相あたりをまず連想します。自分の思いをはっきり打ち出すエネルギーって相当なもの。日頃「感動した!」なんて口に出す機会、なかなか無い。それも土俵上で、となるとまずありません。しかし「答える」エネルギーに匹敵するぐらいエネルギーを要するのが「問う」という姿勢だと思います。本番が始まった途端、打合せ無しの質問の速射砲がゲストを面喰らわせた「顔の無いインタビュー」(「モーニングショー」)や、視聴者の疑問を徹底的に究明した「なっとくいかないコーナー」(「アフタヌーンショー」)を企画・敢行した著者が、一貫して問い続けているのは「テレビでジャーナリズムは実現できるのか」。そこにあるのは視聴率の問題、制作費の問題、スポンサーや人事の問題。パイロット版を売り込むフジTVの編成に始まり、新局12CHでの挑戦~ラジオやU局への企画持ち込み、といった仕事の中で、一つ一つの問題を「これでいいのか」と問い正していく意識。まるで放送界を相手に力強く、それこそ速射インタビューを浴びせているみたい。本著は、インターネット時代についてのこんなコメントで終わる。「個人の在り様いかんでメディアは変わる。インターネットは諸刃の剣。その意味で人間であるあなた自身がまさに問われる時代に入った」読者がゲスト席に座らされたインタビュー番組の始まり。そんな気がします。
2002年3月号掲載『放送禁止歌』(森達也著/デーブ・スペクター監修 解放出版社)
気楽に口ずさめるはずの歌が、一気に社会性を帯びて、芸能が「事件」になるとき。民衆文化には規制はつき物だったのかもしれない。でもここに「放送」というシステムが入ってきた瞬間、この国には独特の力学が生じる。この本の中盤からは、日本人論が主題になっていく。それにデ−ブ・スペクターも登場する。活字なのでデーブの喋り方はいよいよ日本人と見分けがつきません。「表現の自由とは」。しかしこういった見なれたフレーズではすくい取れない、根深いものが、この国の放送禁止歌にはある。それを鮮明にするものの一つが、反体制やプロテストなんてイメージとは程遠い、静かに歌い継がれてきた民謡「竹田の子守唄」。フォークソングとして大ヒットしたこの歌が、非差別部落で生まれた貧しい少女の労働の歌だとわかってきて、メディアが放送を自粛していく。解放同盟からの抗議を考えて。ところが、解放同盟がこの楽曲に抗議をした事実は無いらしい。「ムラではみんな良く歌っていて、放送禁止なんてことを思っても見なかった」と語る解放同盟の役員。タブーは放送する側が作り出してきたのではないか。自ら判断することなく、無自覚に作り出されていく事件。そしてこの「事件」という言葉にも無自覚はある、とデ−ブ。「天安門事件は英語では天安門の虐殺(massacre)と、明確に表記する」英語を使うデーブ、と言うこと以上に目から鱗の1冊。
2002年2月号掲載『決定版!!テレビCM大百科』(エンターブレイン・ムック)
なんでこれほどまでCMって過去を甦らせるのか。そのCMがTVから流れてたころの空気のようなものが、ページがめくられるたびまざまざと思い出されて、なんだかしっとりした気分になってしまった今、いいことを二、三してしまうぐらいの勢いです。「俺もけっこう長く生きてきたなあ」9才ぐらい以上の人なら誰でも懐かしく、楽しめる本と言えましょう。CMが時間をピンナップできるのは思うにあの、毎日何度も繰り返し流れる連打具合なんでしょうね(深夜などほんと容赦なくおんなじCMが立て続けて流れます)。それと、伝えたいイメージが一瞬にギュッと凝縮される密度の濃さ。キャッチコピーってやつがその一端です。この本の、それぞれのCMにキャッチコピーがヘッドラインとして掲げてあるのを見渡すと、まさにそれを思い知ります。もう笑いあり、アートあり、スタイリッシュあり、ペーソスありのイメージメニュー。それにしても五十年代に始まって、CMも成長してきたんだな、と思います。CMっていう媒体の可能性を探っていた60年代、アイデア盛り沢山な70年代、無敵の消費者パワーを感じさせる80年代、画像処理などの技術が物を言い出した90年代・・・と、区分けしたからどうってこともないのですが、とにかく、視聴者の身近な空気を埋めていくこういったCMが、詰まらなくなるような時代がこれから訪れないことを願いたいものです。
2002年1月号掲載『バックステージ・ヒーローズ』(長野辰次著 朝日ソノラマ)
「ドラマ化されない、もうひとつのドラマ」。一口にそう言っても、ステージ上のドラマが作り事なのに対して、それを作ってるバックステージドラマは現実。当たり前のことだけど、この二つは全然別物。ステージをぐるっと取り巻く人々。作家やディレクター、セット作りやナレーションの担当者。それぞれが振り返る、自分たちが今の仕事のやり方を確立してきた瞬間。きっかけは様々。昔から憧れていた職業だったっていうのも勿論あるけど、意外と、やむをえず務めた代役が元で始めていたり、迷っていた時期に出会った人の影響だったり。中には日本でたまたま大相撲を観て英語実況を始めたオーストラリア人だとか、後進の指導に転向した元アイドルなんてケースも・・・。100人を超えるインタビューに共通しているのは、控えめだけど揺るがないプライド。不特定多数の観客のために作られたステージは、実は「特定多数」の思いの結集だったわけだ。自分たちが力を合わせて作った舞台に目線を向ける彼ら。張り切らないわけにはいかない舞台上の人たち。それにしても、ビジネス一辺倒って考え方じゃないゆえの優しさが気持ちいい。貸しスタジオ経営者の言葉。「Kiroroの2人が最初に来たとき、スタジオ代が高いから予約をキャンセルしたいって。キャンセル料がもったいないよって私が無理やりにスタジオに入らせたんです(笑)」
2001年12月号掲載『テレビドラマの職人たち』(上杉純也・高倉文紀著 KKベストセラーズ)
「70年代は脚本家、80年代はプロデューサー、現在は演出家とプロデューサーの時代だ」(まえがき)。役者をどう動かすか、画面をどう作るか。演出家のユニークなセンスを見たい。視聴者の要求はそこまで進化してきてるわけだ。成長するTVっ子。背が急に伸び、声変わりして発毛するTVっ子。そして飽くなき要求に応えんと試行錯誤にあつくなるディレクター軍。「やりたいことは曲げたくない。リアリティって何だろう。リハーサルって必要なんだろうか」。自分たちのこだわりや作品を語る12の個性。でも読みながら感じるのは、ひょっとしたら視聴者ではなく、現場の方が面白いドラマを観たいって欲求が強いのではってこと。今、一線で活躍してるディレクターさんたちは、テレビがめちゃくちゃ元気だった時代を体験してきてるわけだし。影響を受けた番組として挙げられるタイトルを知るうちに作り手の人こそがもっともシビアな視聴者なんじゃないかって思えてくる。「三谷幸喜さんの脚本も面白かったし、個性のある俳優陣で、スポーツ中継みたいに撮ろうと思っていたんですが、撮り始めたら、血が騒いできて派手な演出をするのがやめられなくて・・・」これは『古畑任三郎』をディレクトした星護氏の打ち明け。「血が騒いできて」なんて物作りの理想かも。ドラマというフィクションを作り上げて行く現実。そこには確かな進化がある。
2001年11月号掲載『テレビを面白くする人、つまらなくする人』(放送作家A著 日経BP社)
作家っていうとやっぱり職人。書斎にこもるかロクロを回すかってイメージ。
さてそこで放送作家はどうかってことになると、そんなカタクナなイメージってあまりないわけ。放送作家の作品にあたる「人気番組」ってものに、決まった形なんかないはずだし。本書には、人気番組の作り方ノウハウや、その人気の理由が書かれているけど、その大半は「人気番組の形」を求めて奮闘する、現場での人間の話になっている。バーターによって売れるタレントのこと、長引く会議を抜け出す方法、広末涼子と仲良くなるチャンスのある職種は?・・・見出し的な内容は決して変に深みにはまることなく、サクサクと進み、目まぐるしい放送業界をまさにザッピングしているような印象。たしかにここで批判的に取り上げられていることを読むと、作り手サイドが、視聴者に対してというより、現場のしがらみに対して思いを巡らしてるのでは?なんて言いたくなるけど、TV自体が現実の人間をクローズアップしたがるドキュメンタリー媒体。そう考えれば、トーク台本のためにゲストの面白そうなネタを下準備する作業も、「バラエティにパロディ化されやすいドラマを作れば視聴率が稼げる」なんて関係も、現場の人間のセンスの磨き合いにつながるはずだし、それ抜きにTVってメディアは考えられない。TVならではの魅力って、こういう現場のうねりから生まれてくるように思う。